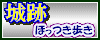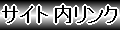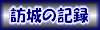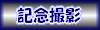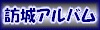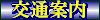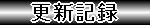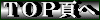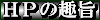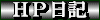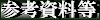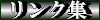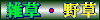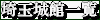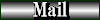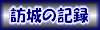 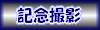
|
�i�@2007/01/27�@�j
�����ݐՏ����ɏł�̐F
�@�u��\�v�Ƃ��������Ȃ��̂͏�i�̐����Ŗ�2,500�u�i�����U�O���A��k�S�O���قǁj�A��i�����̖k���ł͖�1,200�u�i�����R�O���A��k�S�O���قǁj�Ƃ����㉺�Q�����قǂ̕���݂̂ł���܂����B
�l�H�I�ɍ핽����Ă��邱�Ƃ͗����ł��܂����A�������������́u�x�v�Ȃǂɂ��Ă͂قڌ������Ă��Ȃ����̂Ǝv���A�����[�����́u�؊݁v�Ȃǂ��u�������~�v�Ɣ�ׂ�Ɩ��炩�ɕs���ĂȈ�ۂł��B
�@ �����������̓r���ɂāu��イ�����R�v�̓쓌������̎p���f�W�J���ɔ[�߂邱�Ƃɐ����B �܂����R���[�g�̊W�Ŗk���̗ѓ����璼�ړo��ŒZ�R�[�X�����m�ɂȂ�܂������A���_����\���킴�킴�s���قǂ̂��̂��Ɩ����ƁA���Ƃ������悤�̂Ȃ��u�ԐՁv�Ȃ̂ł���܂����B
�@������ɂ���ѓ������甇���オ�郋�[�g�̕����y���ɕ�����₷�����S�̂悤�ł��B �卂�R��������ɉ����ĉ��R���Ă���R�[�X�͓��Ւ��x�̓�������悤�ȂȂ��悤�Ȉ��H�ɂāB
�����ė\��ʂ�̒n�_�ɂĕ���������Ċ���܂ł͗ǂ������̂ł����D�D���R�̌��ʂƂ��ĉ��R���[�g�������i�劾�j �����̗ѓ��܂ł̒����������ŒZ�ŋ͂��Q�O�O���ł��邱�Ƃ����̒��ŕ������Ă��Ă��A���Ȃǂ��o�����Ȃ����Ƃ��F������ł����S���Ɋׂ�������ɂāB
�n�`�}�ƕ��ʎ��𗊂�ɁA���X�t�̐����������𒉎��ɒH������ѓ��֓��B���ĉ��Ƃ����ҁB �������炢���ɖ����Ă����قǍ���Ȃ��A���n�̏�ِՂ����������̂ł���܂����@
�ߑO�P�O���R�O���ɃX�^�[�g�����ԏꏊ�̒H�蒅�����̂͌ߌ�P�T���P�O���B ���ԂƂ��ẮA�卂�R�������R�[�X�n�C�L���O�Ȃ̂ł���܂����B �卂�R�܂ł̃��[�g�͏��w���ł�������\���ɐ������ꂽ�R�[�X�B
�R�������̃A�b�v�_�E�������邽�߂ɁA�����I�Ȕ䍂���͂S�O�O���߂��ƂȂ�v�Z�B �r���卂�R�ւ̃n�C�L���O���[�g�ł͏��w���P�����܂ލ��v�R�g�S�l�̃n�C�J�[�Ƒ������A�P��́u����[���v�Ƃ̈��A�����킷���ƂɁB
�@�卂�R�̎R���ł́A�H�����ۂ炸�ɒn�`�}�ƕ��ʎ������߂ĂԂԂƂ茾�������Ȃ���A���Â����ؗ��̎Ζʂɏ����Ă����Ƃ����������l���ɕϐg�i�����̂��Ɓj�B
���炩�Ƀn�C�L���O���[�g����O�ꂽ�k���̎Ζʂ������Ă䂭�\�j�̎p�́A�e�q�A��̃n�C�J�[���猩��Ƃ��������ٗl�Ȍ��i�ł����������m�ꂸ�B
�@�܂� �卂�R�̐����ɂ͐�ǂ̊�ꂪ�Q�����قǏ��� �������č����͂قڐ����ɋ߂��Q�O���قǂ̒f�R���`���B ����Ԃ����������ł���Ȓn�`�ɑ���������^�̕G�̏�Ԃł͂ƂĂ��˔j�͕s�\�ɂāB
�K���A���Ղ̏����A�t�Ȃǂ̞��̂���A���̏o�����x�ōς݂܂������B ���̕t�߂͑卂�R�̕W���S�W�V�����ō���Ƌ��ɁA�P���Ԃ������ΐl�ƂɒH�蒅����R�̗̈�B
���ꂪ�W���P�炍�O��̎R�x�n��ƂȂ�ƁA���f�R�̑��݂ƂƂ��Ɍk�J���̂��[���A���d������̊댯�������݂��邱�Ƃ͕K��Ɗ̂ɖ����ċ��鎟��Ȃ̂ł���܂��B
|
������@��̕���
�i�@2007/01/27�@�B�e�@�j |
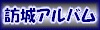
�摜�N���b�N�Ŋg�債�܂�
|
|
|
|
�ʂP�@�����
�@�卂�R�̐����̐藧������łʼnJ�V���▶�Ȃǂ����������Ƃ��ɂ̓n�C�L���O�R�[�X�Ƃ��Ă͂��܂��ʌ����Ƃ͂����Ȃ��n�`��������܂���B
|
|
�ʂQ�@�卂�R�̎R���@���̂P
�@�卂�R�R���̐������������̂悤�Ȋ�ł��`�����Ă���܂����B�S�x�@�\�̖����܂߂ĕW���T�O�O�������̒�R�Ƃ͂����A�����̂̃o�����X�Ƒ����ɕs���̂��铖���Ƃ��Ă͖{�i�I�n�C�L���O�ƂȂ��Ă��܂������Ƃ�����Ɍ�����n�߂�̂ł���܂����B |
|
|
|
|
�ʂR�@�卂�R�̎R���@���̂Q
�@�卂�R�̎R�����炱�̔������Ȃ��Ȃ������炸�A�b���n�`�}�E���ʎ����ɂ߂��������Ă���܂����B���ۖ��Ƃ��Ĕ���������Ƃ������͔��Â����ؗ��̋}�Ζʂɏ����Ă䂭���������N�j�Ƃ����\�����Ó��Ȃ̂����m�ꂸ�B
|
|
�ʂS�@�u��イ�����R�v
�@�e���r��ʂ̕����{�݂̒��p���̏��݂���ӂ肩��́u��イ�����R�v�̓쑤�̗l�q����]���邱�Ƃ�����̂킴�킴����肵���ړI�̂ЂƂȂ̂ł���܂����B
|
|
|
|
|
�ʂT�@���������k���̐��
�@�卂�R���瑱�������͍핽�n�̏���O�ӂ�œ�k�������炻�ꂼ�ꍂ���̎x���ƂȂ�[���J������A�J��������̓o���������㍢��Ȃ��̂ɂ��Ă��܂����B���Ɋ��藎�����Ƃ��Ă��A�Ăє����������Ă��邱�Ƃ͂قڕs�\�Ȓn�`�ł��B |
|
�ʂU�@�핽�n���O�̑�������
�@���̕ӂ�ɖx�Ȃǂ̌`�Ղ��������b���m�F�������̂̂����s���ǂ�������͂��������T�˕��R�ȑ��������������Ă���܂����B
|
|
|
|
|
�ʂV�@�����̍핽�n
�@�����؏ォ����Ղ�����i�̐����̍핽�n�Ŗ�2,500�u�قǂ̍L����L���A�����U�O���A��k�S�O���قǂ̒����𑪂�܂��B
 |
|
�ʂW�@�c���ꂽ�����ؕ���
�@�����̂��߂Ɏc���ꂽ�Ƃ��l������卂�R���瑱�������ł����A�u16�v�̉摜�������悤�ɍ핽�n���̂��W���R�X�O���߂������ł��邽�ߐϋɓI�Ȗ���������悤�ɂ͎v���Ȃ��̂ł���܂����B
|
|
|
|
|
�ʂX�@�c���ꂽ�n�R�̔�����
�@�����̍핽�n�̐�[�������쑤�̒n�R�ł�����������グ�����́B
�@�u�V�ҕ������y�L�e�v�ɋL���ꂽ�u�����R�v�����́u����ԁv���Ƃ���ƁA�m���ɒ��]���̂͗D��Ă�����̂̍����̏W���܂ł̔䍂������Q�O�O���߂����邱�Ƌy�э�̒����݂܂ł̋����̒������Ƃ����_�ł���悤�Ɏv���܂��B
|
|
��10�@�k���̍핽�n�@���̂P
�@�������猩���낵���k���̍핽�n�̗l�q�ł����A���̕ӂ肩�瓥�ݐՂ��s�N���ƂȂ荱���Q�Ă邱�ƂɁB
�@�������A�悭�l���Ă݂��200���قǐ�ɂ͗ѓ��������Ă���A�����֍~��Ă��ѓ��̋߂��܂ł͍s����͂��Ȃ̂ł���܂����B
|
|
|
|
|
��11�@�k���̍핽�n�@���̂Q
�@�����̖k���ł͊��������A��1,200�u�قǂ̍L���łŕ����ɂ��Γ����R�O���A��k�S�O���قǂ̋K�͂�L���Ă��܂����B
|
|
��12�@�k���̍핽�n�@���̂R
�@�E��̖k�������ɐi�߂u�������q��v���o�Ċ��q���̌Ó��ւƌ������͂��ł��B
�@ |
|
|
|
|
��13�@����Ԃւ̓o���
�@���̃R���N���[�g�̗i�ǂ̊Ԃ��璼�o����Δ䍂���X�O�����炸�Ȃ̂łQ�O���O��ʼn��̕���ւƓ��B����͂��ł��B�@�������A���͂��قǗǍD�ł͂Ȃ����ݐՒ��x�ł����A�Ђ�����^����������i�߂Ζ������Ƃ͂���܂���B�������t�����X�ɔɐB���Ă���̂ŗv���ӂł��B
 |
|
��14�@�����ЂƂ́u�����R�v�̔��n
�@��イ�����R���猩�ē����̒J���u�Ă��n�`�ŕ����R�Ə̂��ׂ��n�_�́u����ԁv�ȊO�ɂ́A�u����ԁv�̖k����S�O�O���̒n�_�ɏ��݂���A���̉摜�̍����̔����ؐ�[���̕W���Q�W�O���i�@�䍂���P�O�O���ō�̒����݂܂ł͔����ȉ��̋����@�j�̃s�[�N���z��ł�����̂ƍl�����܂��B
 |
|
|
��15�@����Ԃ̉��]
�@�u�鈧�l�v�Ǘ��l�ł���j�i�ǂ̂Ƃ̋A�H�̓r���ɂāA���̓~�������[�J���Șb����W�߂��C�m�V�V�^�̐d�X�g�[�u���������Ă���H��̋ߕӂ��炠�炽�߂āu��イ�����R�v�Ɓu�������~�v�̎p���m�F���Ă���ƁA���R�ɂ��u����ԁv�̏��݂��镽�R�n�������Q�X�X�������疾�Ăɖ]�߂�̂ł���܂����B���x�����̓������������A���܂܂ŋC�Â��Ȃ������^�̂܂��ɕs���̒v�����ɂČ��B
�@���܂ł͂��̃��[�g�𑖍s���Ă��}�J�[�u�̑������Ƃ����萸�X�u��イ�����R�v���ʂ���˂�����x�ɂāB���_���猾���A���̒n��̃C���[�W���������̒��ō��ׂƂ��Ă���Ƃ������Ƃ��ĔF����������Ȃ̂ł���܂��B
�@�@�@�i�@2007/03/31�@�B�e�@�j
|
|
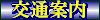
�E�卂�R�k����S�O�O���̔����ɏ���
�E�����K�C�h �̈ē��}�ł��@ �@ �@
|
�ʒn���ށE�j���E�Õ����Ȃǂ̋L�q
���V�ҕ������y�L�e
�@�����S�쑺�̍��ɁA�u�肤�����R�@���̓�ɂ���@�y�l�����Z�푾��������ՂȂ�Ɖ]�@�D�D�D�o�邱�Ə\������@���㕽�R�ܘZ�\�@�����y�юG�ؐ����@�x�Ί_���̌`�͑�����@ ����蓌�̕��J��j�ā@�����R�Ɖ]����|�����@�k�̕��։��鎖�ܘZ������̏��Ɉ����Ђ̏��K����@�����Ɏl�ܕS���̕��n���营�𒆉��~�Ɖ]�v�ƋL����Ă��܂��B
�������u
�@���Ӓn����܂߂Č������Ă��邽�ߋ�̓I�ȋL�q�͂���܂���B
|
�ʎ�ȎQ�l����
�u��ʂ̒�����ِՁv�i1988/��ʌ�����ψ���j�E�u�֓��n���̒�����فv�Q��ʁE��t�v�i2000/���m���сj
�u�����k�����̏�v�i�~�v�v�@���@2003/��c���@���j�E�u�V�ҕ������y�L�e�v(1996/�Y�R�t)
�u�������S���j�v(1954/��ʌ�)�E�u�p����{�n���厫�T�P�P��ʌ��v�i1980/�p�쏑�X�j
�u��ʌ��j�@������10�ߐ��P�n���v(1979/��ʌ�)���u�����u�v�u�������H�v�Ȃ�
�u�є\�s�j�@�ʎj�ҁv(1988�N/�є\�s���s)�E�u�є\�s�j�@�����ҁ@�n���E�����v(1986�N/�є\�s)
�u�є\�s�j�@�����ҁ@�������v(1976�N/�є\�s)�@
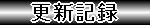
�E2007/05/19�@�g�o�A�b�v�����������E�lj�
|