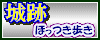 |
  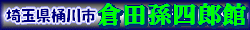  |
|
|---|---|---|
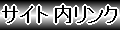 |
2006/05/08の日記 加納城 加藤氏館 小高氏館 | |
| おすすめ評価 |
|
|
|
|
埼玉県桶川市大字倉田 | |
|
|
■謎の倉田氏? |
|
|
|
土塁、空堀 | |
|
周辺の地理的特徴 |
■大宮台地北東の端に位置し1kmほど離れた綾瀬川に向かって緩やかな傾斜があるようですが周辺の地形は、見た目ではほぼ平坦地としか見えません。南側を除く三方向のやや離れた辺りに水田地帯が存在していたものの、現在の状況から見た限りでは天然の要害という地形には程遠い地形です。 |
|
|
|
無 | |
|
|
2006/05/08 |
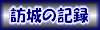
|
||||||||||||
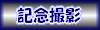
|
||||||||||||
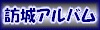
|
||||||||||||
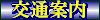 |
||||||||||||
|
凸地誌類記述の状況
「新編武蔵風土記稿」 足立郡倉田村の項では「入間郡法恩寺の年譜録に云う、文治2年(1186)隣県之令有倉田孫四郎基行者、この当郡市刺史児玉武蔵守・藤原惟行家弟而為河内守、越生次郎家行の叔父なり、有所以退隠于倉田の邑...」と記されていることから、児玉党の系譜をひく倉田孫四郎がわけあって倉田村に隠居したと解されます。 また、入間郡今市村の項では更に詳細に法恩寺の年譜録を引用し、倉田孫四郎夫婦がともに仏門に入り瑞光坊、妙泉尼と称し法恩寺の再興を源頼朝に願い出たので、直ちに越生次郎家行に命じてこれを再興させ、吾那(吾野)の3百町を瑞光坊、妙泉尼の2人に与えた旨が記されています。しかし、児玉党系図と対照して倉田氏を名乗る人物が不在なこと、また「新編武蔵風土記稿」の越生氏の出自に関する推論などと照合すると、その年代が100年以上合わないことから年譜録の記述に疑問が残ります。 「武蔵志」記述なし 凸参考資料
「中世北武蔵の城」(梅沢太久夫 著 2003/岩田書院刊) 「埼玉県史 通史編1古代」(1987/埼玉県) 「埼玉県史 通史編2中世」(1988/埼玉県) 「埼玉県史 別編4年表・系図」(1991/埼玉県) 「新編武蔵風土記稿」(1996/雄山閣) 「武蔵国郡村史」(1954/埼玉県) 「角川日本地名大辞典11埼玉県」(1980/角川書店) 「埼玉県史 資料編10近世1地誌」(1979/埼玉県)より「武蔵志」「武蔵演路」など 「桶川市史 第3巻 古代・中世資料編」(1985/桶川市) 「桶川市史 通史編」(1990/桶川市) |
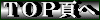 |
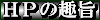 |
 |
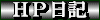 |
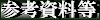 |
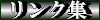 |
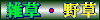 |
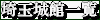 |
PAGEの先頭 | PAGEの最後 | ご感想はこちらへ | 工事中 |