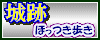 |
 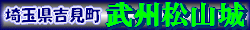   |
|
|---|---|---|
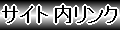 |
2007/01/13のブログ 伝源範頼館 御所陣屋 御所堀 大串次郎館 | |
| おすすめ評価 |
|
|
|
|
埼玉県比企郡吉見町南吉見字城山ほか | |
|
|
|
|
|
|
主郭、二の郭、春日郭、三の郭、惣郭、兵糧倉、物見櫓台、土塁、空堀、竪堀、小口 | |
|
|
|
|
|
|
1924年3月31日 埼玉県指定史跡 | |
|
|
2007/01/10、01/13、02/23、04/19 |
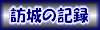 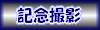
画像クリックで拡大 ( 2007/01/13 撮影 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
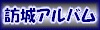 全て画像クリックで拡大します 2007/01/10 撮影 以下同様
2007/01/13 撮影 以下同様
2007/02/23撮影 以下同様
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
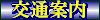 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
凸地誌類・史書・古文書などの記述
■新編武蔵風土記稿 横見郡根小屋村の項に「松山古城 連山の端にあり、是を望めば孤山の如し、麓に市野川を帯び、南に深田あり、巌石直立す、古は頂上よに池水をたたえしが、今は埋みたり、天然の要害なり(以下省略)」と、その地勢の特徴にについて詳細な挿絵とともに記述されています。 ■武蔵志 「松山古城」としての由来のほかに周辺の地形の特徴を記した「松山古城之図」が描かれていると同時に、「兵糧曲輪」(西の曲輪)で「焼米」がよく見つかるという旨が記されています。 ■「岩殿山正法寺縁由」 天正18年の攻防戦について「当城の留守居難波田因幡守..比企藤四郎、そのほか軽率所民駈集の都合弐千人立篭る。前田利家は大手に向かい、上杉景勝は搦手より寄られ、其余諸将大道寺父子、城々の降兵等城の四辺を取り囲み、諸手一同に鬨の声を作り、大鉄砲を放懸ければ、塀も櫓も打崩れ、当城は既に危うく見えたりける時に、住観房は上田の家臣藤四郎方に居合いければ数多の士卒の討死させんも不憫なりと思い、僧の事なれば和睦の媒となり、上田の幕したは降参して城を敵に明け渡し」とその様子を伝えています。(「吉見町史」より引用) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
凸主な参考資料
「埼玉の中世城館跡」(1988/埼玉県教育委員会)・「関東地方の中世城館」2埼玉・千葉」(2000/東洋書林) 「中世北武蔵の城」(梅沢太久夫 著 2003/岩田書院刊)・「埼玉県史 通史編2中世」(1988/埼玉県)・ 「埼玉県史 資料編6中世2古文書2」(1985/埼玉県)・「埼玉県史 資料編8中世4記録2」(1986/埼玉県)・) 「新編武蔵風土記稿」(1996/雄山閣)・「武蔵国郡村史」(1954/埼玉県)・「角川日本地名大辞典11埼玉県」(1980/角川書店) 「埼玉県史 資料編10近世1地誌」(1979/埼玉県)より「武蔵志」「武蔵演路」など 「吉見町史上巻・下巻」(1978/吉見町)・吉見町の公式HP・「戦国期の松山城」(リーフレット/吉見町立埋蔵文化財センター) 「東松山市史資料編第1巻」(1981/東松山市) 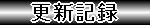 ・2007/04/30 HPアップ |
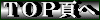 |
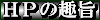 |
 |
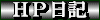 |
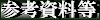 |
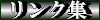 |
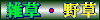 |
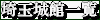 |
PAGEの先頭 | PAGEの最後 | 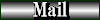 |
工事中 |