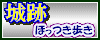 |
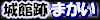    |
||
|---|---|---|---|
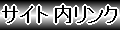 |
2006/12/01のブログ 羽尾千躰地蔵裏山 羽尾堀の内 羽尾愛宕山 羽尾大沼 | ||
|
|
埼玉県比企郡滑川町羽尾平周辺 | ||
|
|
平場(堂宇跡か)、古墳 |
|
なし |
|
周辺の地理的特徴 |
凸気になる地形だらけで |
||
|
|
2006/12/01 | ||
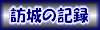 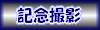
( 2006/12/01 撮影 ) |
||||||||||||||||||
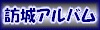
|
||||||||||||||||||
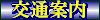 |
||||||||||||||||||
|
凸主な参考資料
「埼玉の中世城館跡」(1988/埼玉県教育委員会)・「関東地方の中世城館」2埼玉・千葉」(2000/東洋書林) 「中世北武蔵の城」(梅沢太久夫 著 2003/岩田書院刊)・「新編武蔵風土記稿」(1996/雄山閣) 「武蔵国郡村史」(1954/埼玉県)・「角川日本地名大辞典11埼玉県」(1980/角川書店) 「埼玉県史 資料編10近世1地誌」(1979/埼玉県)より「武蔵志」「武蔵演路」など 「滑川村史 通史編」(1984/滑川村編集発行)・「滑川村史 民俗編」(1984/滑川村編集発行) 「滑川村史調査資料 第4集 旧羽尾村・設楽家・小沢家・小林家・上野家」(1980/滑川村村史編纂室) 「滑川村の沼とその民俗」(1981/滑川村村史編纂室) 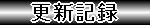 ・2007/01/15 HPアップ |
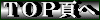 |
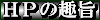 |
 |
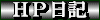 |
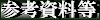 |
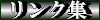 |
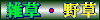 |
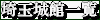 |
PAGEの先頭 | PAGEの最後 | ご感想はこちらへ | 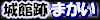 |