|
|
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 関連ページのリンク | 2005/06/21の日記 東本庄の館 北堀堀ノ内 栗崎館 | ||||
| おすすめ評価 |
| ||||
| 埼玉県本庄市大字西富田461付近 | |||||
■選択を誤り衰退していった一族
| |||||
| 土塁、空堀 | |||||
周辺の地理的特徴 | ■館跡の100mほど南側を流れる女堀川の北に位置し、当時はその流れを利用した水濠であった可能性があります。遺構としては鈍角に屈曲している部分の堀跡の一部分とその付近の土塁が残されているようですが、このことだけから全体の規模を想像するのは難しいようです。 | ||||
記録 |
「中世北武蔵の城」(梅沢太久夫 著 2003/岩田書院刊) | ||||
| 無 | |||||
| 2005/06/21 |
( 2005/06/21 )
| ||
| Best Shot? |
手前の路地の微妙な曲がり方も堀跡の形状に伴うもののようです。 堀跡は大分埋め垂れられたとのことでしたが正面の屋敷林の手前側に深さ1m、少なくとも延長10メートルほどの空堀と高さ2mほどの土塁状の連続した土の塊が確認できました。なお、左手前の部分が平坦地となっていましたので埋められた堀跡かも知れません。 ( 2005/06/21 撮影 晴 ) | |

|
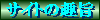
|
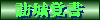
|
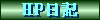
|
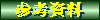
|
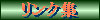
|
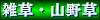
|
工事中 | PAGEの先頭 | PAGEの最後 | ご感想はこちらへ | 工事中 |