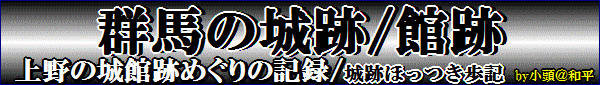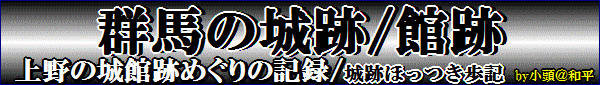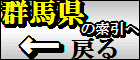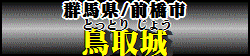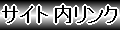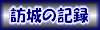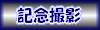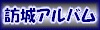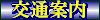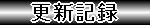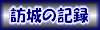 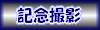
|
凸 一日は2万歩まで
城館跡の西側には藤沢川が流れており、その堰堤上を北に向って歩いていると右手(東側)の民家裏に人工的な地面の高まりが目に入りました。 現在の堰堤が整備される以前の古い堤防か、民家の屋敷神などを祀るための築山か、あるいは城館跡の残滓であるのかについては不明です。 さらに北へと歩みを進めていくと右手方向に折れてゆく小道がありましたが、どうやらこの小道が城館跡の北限に相当するものと思われたことから、そのまま上武鳥取交差点へと向かう市道を横断して、城館跡の東側へと向かうことにしました。
また途中の民家宅地境には、ほんの僅かですが土塁と堀跡のように見えなくもない地形が残存していましたが、むろん後世における屋敷の風除けのための土塁である可能性も考えられるなどと思いつつ先を急ぎました。 当城跡の中心部付近には大鳥神社が所在し、神社の解説板に僅かにこの城館跡に関する記述を見ることができます。 なお現在では当該砦跡の中心部には金型製造の工場が所在しています。
さて、この時点で時刻は未だ午後1時半過ぎでした。 それでも午前中は吹きまくっていた北寄りの風も弱まり、少し暑いくらいの春先の陽気となってきました。
しかし今回は約2か月以上のブランクが存在していました。 一向に改善されない様子の変形性股関症の可能性などの問題もあり、今回は殆ど遺構が現存していない文字通りの城館跡ではありましたが、すでに当初の目標であった以上の6個所を廻り終えていたこともあり、別途内反小指の痛みを感じ始めたところで撤収を即断いたしました。
なお今回の探訪先はほぼその全てが赤城山の南麓に位置する城館跡であり、赤城山の中腹辺りに水源を有する小河川による浸食谷によりその東西方向が防御されることとなるという共通性を有しています。 また上武道路を挟み北約1kmに所在している勝沢城とは東西を流れる小河川が共通していることにあらためて気づきました。
今回は全て車で近くまでアプローチして最短距離を歩くことも考えたのですが、次第に足の動きも軽くなってきたこともあり、足の感触を確認すべく結局約2万歩ほどの行程となりました。
その結果、平地であるとはいうものの当初の懸念とは裏腹に、歩幅とスピードについては問題があるもののどうにか歩行できることだけは確認できました。
尤もそのことが比高差を有する山城方面への適応力となるのかどうかについては、自分の体ではあるが今のところは何とも分からないというのが現状でした。
今後に再び山城方面へ向かうとしても、あと少なくとも2度くらいは平地を歩き足回りの引き続きその様子を観察しておくべきであろうとも感じました。
帰路は上武鳥取町の交差点から再び上武道路を経由したが、花粉症の症状は継続する明確な目のかゆみとして現れていました。 また帰宅後に鼻腔の周りを検証してみると明らかに花粉の塊と思われる物質が付着していたので洗面所にてきれいさっぱりと洗い落としました。
たぶん少なくともこうした症状はあと1か月くらいは続く感じがするのですが、今年の花粉症の症状はとりわけ目に来るという傾向があるようでした。
( 2019/4/2 )記述
|
鳥取城西域附近の地形 −画像A−
( 2019年3月14日 撮影 )
凸城館跡の西側(画像の手前部分)には藤沢川が流れており、その堰堤上を北に向って歩いているとの右手(東側)の民家裏にこのような感じの人工的な地面の高まりが目に入りました。近年に樹木等の伐採が行われたことにより目につきやすくなったいう印象はありますが、足元からの高さは3m近くあるように思われました。
おそらくは現在の堰堤が整備される以前の古い堤防か、民家の屋敷神などを祀るための築山か、あるいは城館跡の残滓であるのかについては不明なのですが、その後いろいろと調べておりましたところ、この付近でかつての藤沢川の川道が大きく東側(画像の奥方向)に蛇行していたことが分かりました。従ってこのことに起因する地形である可能性が高いのですが、それでもその全てが河川の蛇行とこれに伴う築堤工事によるものであるのかまでは断定できないようにも思われました。
鳥取城の北西部付近 −画像B−
( 2019年3月14日 撮影 )
凸鳥取城北辺部の西側付近の低い河岸段丘状の地形のようにも見える画像です。 城跡としての領域はこの画像の屋敷林の所在する右側部分であると推定されていることから、画像左側の石積みは領域外となるためあくまでも後世のものであるのかも知れません。
なおこの画像の右手付近の民家宅地境には、ほんの僅かではありますが土塁と堀跡のように見えなくもない地形が残存しているように見受けられましたが、屋敷の北西方向でもあることからむろん後世における屋敷の風除けのための土塁である可能性も考えられます。
大鳥神社の文化財解説板 −画像C−
( 2019年3月14日 撮影 )
凸現在鳥取城跡の中心部付近にはこの大鳥神社が所在しており、この神社の文化財解説板のなかに僅か2行ほどですがこの城館跡に関する記述を見ることができます。
国土地理院航空写真 −画像D−
( 2019年4月1日 編集加工 )
凸赤色の破線で囲んだ個所が鳥取城の領域であると考えられているようです。現在では城跡のすぐ北側には大正期に建設された灌漑施設である「大正用水」が流れ、この画像には書き入れませんでしたがそのさらに北側には国道17号線バイパスでもある「上武道路」が東西方向に縦断しています。
一見しますと北方の丘陵続きの部分がこの城館跡の地形上の弱点であるように感じられますが、仮に古河公方、扇谷上杉氏勢力を意識した場合には、主に南と東にその防御の重点を置くものと考えられることからそれなりの整合性は保たれているのかも知れません。
|