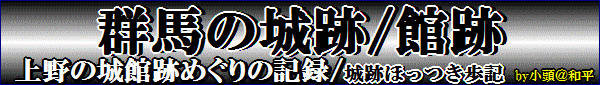 |
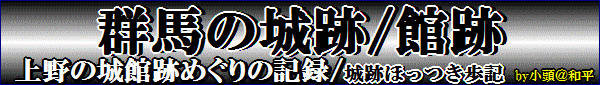 |
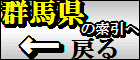 |
 |
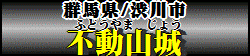 |
 |
|---|
| 1歴史・伝承 2残存遺構 3訪城記録・記念撮影 4アルバム 5交通案内 6参考・引用資料 7更新記録 |
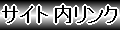 |
2018年4月5日のブログ 凸長井坂城 凸阿阻城 凸猫城 凸棚下の砦 | ||||
|
|
群馬県渋川市赤城町見立二城、このほか城域の一部は樽、宮田にもまたがる |
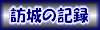 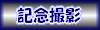
( 2018年4月5日 撮影 ) 凸現状では「追手」(大手)と記されている個所から横堀を渡るルートはほぼ通行できるような状態ではなく、まず土橋状の地形確認等も困難であるように感じられました。
( 2018年4月5日 撮影 ) 凸この山道をそのまま道なりに進むと主郭南側の腰郭部分に到達するのですが、足元の道も極めて良好で腰郭までは僅か200mほどの距離しかありませんでした。なお、史跡としてある程度整備されているとはいえ、あくまでも足元が無論スニーカーなどの場合をいうのでありまして、中世城館の場合には街中で履くような普通の革靴やハイヒールなどは向いておりませんのでくれぐれもご注意を願います <(_
_)>
( 2018年4月5日 撮影 ) 主郭(画像上)と腰郭(画像手前)の様子ですが、主郭部の虎口についてはこちらの西側では確認できず、竹藪のある画像の無右側奥であると考えられているようです。
(⇒下記の画像F参照)
( 2018年4月5日 撮影 ) 凸現状では腰郭から主郭へと続くルートはこの利根川沿いの崖線脇を通過しています。見学者に配慮したと思われる細い支柱と虎ロープとが設置されてはおりましたが、ほぼ破損しているというような按配ですので、ストックなどを携行していれば寧ろ木の枝などに掴まり切岸を直登した方が安全なのかも知れません。( ⇒ あくまでも2018年4月5日現在での感想です)
( 2018年4月5日 撮影 ) 凸南西方向に続く主郭直下の腰郭と細尾根で搦手のような印象もありましたが、既にこの時点で5か所目ということもあり疲労のため足元がふらついており先端部は未確認です (^^ゞ
( 2018年4月5日 撮影 ) 凸主郭部(本丸)を東西に分ける窪み地形で、「ぐんまの城30選」などでも、南側腰郭からの虎口と推定されている模様です。腰郭付近からの入口は竹藪が目立ちますが、より安全に主郭部へとアプローチするにはこちらのルートもそれほど悪くは無いように感じました。
( 2018年4月5日 撮影 ) 凸主郭東側の郭2とその北東部の郭を隔てている堀切で、この城の見どころのひとつのはずなのですが、残念ながら真竹の叢生により画像左側の堀跡をすすむことは困難でした。堀の深さは郭2側でも3m以上で、画像左側の北東部切岸の高さは5m以上はありそうに見えました。
このあと切岸を這い上がり、いちおう郭面の地形だけでも確認しようと試みたのですが、ストックを使用しても藪に阻まれ進退が窮まっている最中に下記のカモシカに出会い敢え無く撤退しました。このため宮田不動尊方面の尾根筋も未確認です。 なお山崎一氏が作成されたと思われる縄張図には、この地点から北西方向に向けた長大な竪堀が描かれておりますが、自然地形の谷を過大に評価している可能性を感じ、いちおう現地を確認しようと考えておりましたが、生憎下記画像に示す2頭のニホンカモシカと遭遇し、結果的にその確認作業を阻まれることとなりました (^^ゞ
( 2018年4月5日 撮影 ) 三の郭方面への移動中、トレッキング用のストックを使用しても登攀に難儀しているという真っただ中に出会ったカモシカ (特別天然記念物ニホンカモシカ)です。この画像ではこの1頭だけしか映っておりませんが、少し手前から廻りこんで観察したところ仲良く2頭でじっとこちらを凝視していたのでありました。斜面であがいている最中にふと視線のようなものを感じたので、ストックを斜面に刺して体を安定させ左手前方を眺めたところガッチリと視線が合いました (^^ゞ
このカモシカの背後は斜度約50度前後、比高差約100mの急崖でしたが、流石にカモシカだけあってバランスも良く悠然としておりました。無論クマやイノシシではないので、「驚かすような行動をとらない限りはこちらに向かってくるようなことはない」旨を耳にしてはおりました。そうはいうもののこちらの方も足元が余り良好ではなく、体重の比較ではこちらの方が約2倍ほどはあるにしても、彼我の距離が約5mほどとかなりの至近距離であったこともあり、できるだけ刺激をしないようにゆっくりと撤退することとなりました。
( 2018年10月24日 編集加工 ) 凸「堀跡遺構」の「い」(外側の堀)「ろ」(直角に曲がる堀)「は」(主郭と郭2の間の堀、主郭部は「は」の文字の下あたりと推定)については現在でも概ね確認ができます。終戦直後の画像であるため現在は竹林となっている個所は耕作地として開墾されている様子も窺われます。
|
||||||||||||||||||||
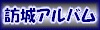
|
||||||||||||||||||||
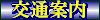 大きい地図・ルート検索 ( powered by ゼンリン地図 いつもNAVI ) |
||||||||||||||||||||
|
凸参考・引用資料
(太字の資料は特に関連が深いもの、あるいは詳しい記述のあるもの) ■城郭関係 ■歴史・郷土史関係 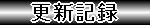 ・2018年10月29日 HPアップ
|