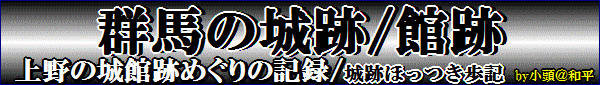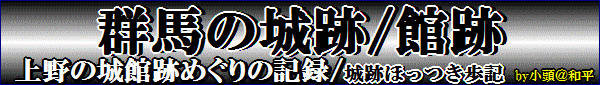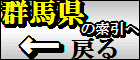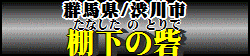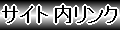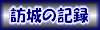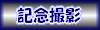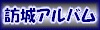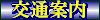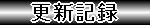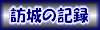 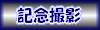
|
凸 尾根筋はどこだ?(長い前置き)
なんと4月2日に続いて2日おきの城館探訪でした。ある程度気力と体力がありそうに感じられ、かつ天候がまずまずであれば即座に出かけるという以外の選択肢はないのであります。
とはいうものの目的地が群馬県渋川市(旧赤城村)方面であることから、拙宅からは上武道路が延伸されているとはいえ片道約120kmですので、一般道を利用居る場合には通常約3時間半前後と予想される些か遠い道程となっております。
このため今回は朝方の渋滞混雑を避けるべく、早朝の午前5時前に自宅を出発することとしました。
今回はいちおう5か所ほどを予定したましたが、そのうちの平地の2か所については時間に余裕があれば立ち寄るというもので、今回の城館探訪についてあくまでも3か所の山城が中心となるのであります。
幸いにして現地に到着したのは早朝の走行ということもあり、途中2度の休憩を挟んだにもかかわらず午前8時には現地付近に到達していました。
ところが昨年訪れた長井坂城の近くであるにも拘らず、結果的には現地ではその目的地探しに40分ほどを費やすこととなってしまいました。
他の方のネット情報などにもあるように農道や高速道路の側道やらが複雑に入り組んでおり、なかなか即座には到達できにくい所在地のようなのです。
もっとも現地の地形や高速道路の位置などに鑑み、なかばヤマ勘を働かせて訪れた当初の場所が結局のところ最も該当地に近接していたのですが、付近の道路が複雑に配置されているようでこのような仕儀となりました。
無論カーナビのガイドは農道などの道路事情も正確には反映されておらず、余りあてにはできなかったこともありました。それにしてもこれほどまでに迷ってしまったのはここ20年ほどの記憶の中では多分初めてのような気もするくらいなのでありました。
凸 さて、ここからようやく本題です
肝心の城跡は関越道のすぐ西側の東西に伸びる尾根筋に所在していました。定石通りに北側の尾根筋基部からアプローチしましたが、関越道東側の林道が谷筋を超えるべく大きく南西方向にカーブした個所が城跡への入口でした。しかし長井坂城のような入口の案内板などは全くありません。強いて言えば関越道西側に所在するやや小ぶりの送電線鉄塔が目印なのかも知れないのですが、これが遠くからでは全く目立ちません。
車は本来の林道から西へと分岐した路肩へと停め、やや荒れ果てた感じのする舗装済の林道を道なりに約100mほど進みます。するとその林道は180度方向を変えて再び東側の関越道側へと戻ってしまいます。このためこの林道からは外れるようにして、そのまま目の前の踏み跡程度の樹林帯を西へと前進していきます。なお、近年まではこの林道から真直ぐに西へと延びる踏み跡が存在していたようなのですが、周辺の樹木伐採によりかなり見通しは良くなっているものの、現在当該踏み跡は伐採された樹木が林道道路上に広がりそのまま進むのは困難となっていました。無論よくよく見れば2か所ほどの新しい踏み跡が確保されているので、何れかをそのまま西に進めば約50mばかりも歩くと東側の二の郭と馬出との間の堀跡に到達してしまいます。
城館としての見どころはこの堀跡と馬出のほかに標柱の所在する主郭などがあります。なお、主郭西側下の小郭はそのまま利根川の崖線部先端となっており断崖の比高差は明らかに約100m以上を有すしています。かつては棚下不動堂方面からの登攀ルートも存在していたらしいのですが、斜度、斜面状況、足場の悪さなどから見るかぎりでは全く降りてみようという気にはなりませんでした。比高差はアプローチが林道からの下り道なので事実上ゼロであり、いくら堀跡や切岸の登りを累計しても20mには届かないというのは誠に嬉しいものがあります ^^
( 2018/4/30 )記述
|
堀跡 −画像A−
( 2018年4月5日 撮影、以下同じ )
凸いきなりその姿を現す堀跡です。いちおう山城の部類に入ることから堀切といってもよいのですが、対岸には馬出があり、その向こうに主郭部が続くという変わった形ではあります。単純に直線的な堀切ではなく尾根筋を斜め方向に掘削して、しかも半円形の馬出の存在により結果的には弧を描いた形となっています。
東郭の西端部 −画像B−
( 同前 )
凸近年の林道建設などにより一部遺構が失われてしまい、その現状からは余り工夫が感じられない東の郭ではあるのですが、主郭部にほど近い西端部になると俄かに城跡らしい普請がそこかしこに現れてきます。前項の画像Aでも堀切られた平面形状が弧を描いていますが、この西端部の北側でも東郭の一部がそのまま西側方向に細く伸びて恰も土塁状の地形を呈しています。砦跡の尾根筋は東西方向に伸びていますが、その南北には深い鈩沢やケヌキ沢の谷が所在しているため、南北方向からのアプローチはほぼ困難ではないかと考えられます。この土塁状地形の北側下方には腰郭状の削平地があり、この堀切地形はその腰郭地形の西側でやや浅めの竪堀状地形へと続くようになっています。
堀切 −画像C−
( 同前 )
凸画像右側が土塁のある馬出の切岸で、左側は東郭の切岸に相当し、堀幅も広くともに深さは4mほどですが、この規模の城館としては規模の大きな堀切地形です。
主郭東側の堀 −画像D−
( 同前 )
凸主郭東側の堀跡(堀切)で桝形のようにも見えますが、些か広すぎるようにも思える地形です。画像左側が馬出の切岸、画像右側が主郭切岸となり、二つの郭は奥に見える細い土橋状の地形により繋がっています。
馬出 −画像E−
( 2018年月日 撮影 )
凸東側堀切(画像の奥)の前面に土塁を伴った馬出と考えられている部分です。この画像からは分かりにくいのですが、削平地としての規模は小さく仮に長柄の槍を携行しているとすると多くとも数人程度が守りに着くくらいの広さしかありません。但し、堀切の対岸に正対するとともに、主郭部虎口を主郭側土塁部と両側から囲む形であることから有効な防御効果を果たしていたであろうことが想像されます。
主郭の標柱 −画像F−
( 2018年月日 撮影 )
凸「史跡」と明記されてはいますが、合併以前当時の「赤城村歴史散歩の会」により設置された標柱で、合併後現在の渋川市での史跡指定はされてはいない模様です。そうした行政上の経緯は別として、一般にはあまり知られてはいない山城跡にこうした標柱が存在していること自体がたいへん有難いものを感じます。
主郭から馬出 −画像G−
( 2018年月日 撮影 )
凸主郭部の東側土塁上から馬出とこれに続く細い土橋状の地形を眺めている構図です。今回50枚ほどの撮影のなかでは管理人が最も気に入っている画像であります ^^
利根川の大蛇行 −画H−
( 2018年月日 撮影 )
凸西崖下を大蛇行する利根川を俯瞰した画像です。眺望は正しく絶景ですが、この地を訪れる方は一般には余り知られていないこともありそう多くは無いものと思われます。無論安全柵や転落注意などの表示もない私有林の断崖ですので、あくまでも自己責任でおいでいただくことととなります。下記画像の16とほぼ同様の位置から撮影していますが、あと50cm進みますとそのまま崖下へと転落する恐れがありました (^^ゞ
|