| 城館跡の名称 |  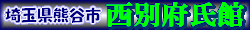 |
|
|---|---|---|
| 関連ページのリンク | 2005/09/15の日記 東方城 別府城 | |
| おすすめ評価 |
|
|
|
|
埼玉県熊谷市西別府 | |
|
|
■成田氏の一族の館の一つ |
|
|
|
概ねなし | |
|
周辺の地理的特徴 |
■別府氏から分かれた西別府氏は東別府氏に比べると恐らく早い時期に衰退した模様で、「新編武蔵風土記稿」が伝えているように館跡などの遺構も東別府氏のものと比べると現在はほとんど残されていません。西側約1キロメートルに所在する深谷上杉氏の勢力下にあったと考えられる東方城などと同様に妻沼低地を望む櫛引台地の北端に位置しています。また、東南東約1キロメートルには同族の東別府氏の城館跡があります。 |
|
|
記録 |
「中世北武蔵の城」(梅沢太久夫 著 2003/岩田書院刊) |
|
|
|
無 | |
|
|
2005/09/15 |
|
|
( 2005/09/15 ) |
|
| 記念撮影 |
約70年前の昭和11年3月に別府史跡保存会が建立したと裏側に刻まれている「史蹟 西別府舘址」の立派な石碑。最近礎石の部分を建て直した際にきれいにリフォームしたようです。ちょっと見ただけでは新品同様になっていましたので、建立の年月を見てやや意外な印象が。 ( 2005/09/15 撮影 晴れ 微風 ) |
|
| 訪城アルバム |
■①北側にある別所沼。暑さや水流の関係で藻が異常に繁殖したらしく沼の水面が全く見えませんでした。
■②館跡の北側部分。この木の下が別所沼になり、沼地との比高差は約4mほどの違いがあります。
■③天満天神宮の祠で、館跡の中心部分辺りからはおおむね丑寅の鬼門の方角に当たります。
■④現在は主に人工の還流水が流れている小河川の跡(堀跡)で、別所沼の低湿地とあわせて水堀のようなものが形成されていたのでしょうか。この元河川の流れは別所沼を通り北側を流れる福川に合流しやがて利根川に至ります。また、当時の様子は不明ですが現在は用水路としての掘削により東方城の北側を流れる小河川とも繋がっていることがわかりました。
■⑤湯殿神社の南側の参道入口と⑥の祭祀遺跡の標柱。
■⑥東側の堀跡の方から見た湯殿神社(正面)で、祠の左側にかつては湧水が湧く堀があり奈良時代には水神を祀る儀式が執り行われたと推定されています。(熊谷市指定史跡)
■⑥臨済宗安楽寺の別府甲斐守頼重とその夫人の墓所
(1936年3月11日埼玉県指定史跡) ■⑦上記⑥の現地解説版。
|
|
|
|
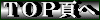 |
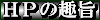 |
 |
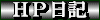 |
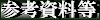 |
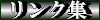 |
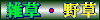 |
工事中 | PAGEの先頭 | PAGEの最後 | ご感想はこちらへ | 工事中 |