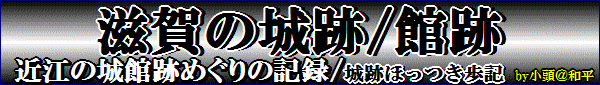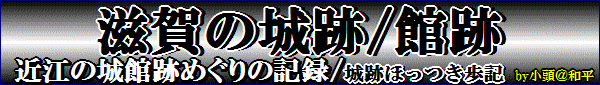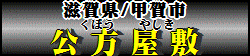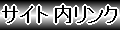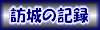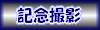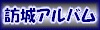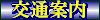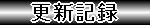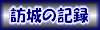 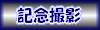
|
凸 急いては事を・・・
この日は早朝からの京都行新幹線移動の後に琵琶湖線、草津線とJRの在来線を乗継ぎ、ようやく油日の駅に到着しました。自宅を出てから約6時間で、時刻は既に午前10時半を大きく回っておりましたが、行動時間に余り余裕もないことから、そのまま飲まず食わずで殿山、殿山城、公方屋敷支城と廻っていたこともあり、あまりの空腹と喉の渇きに苛まれ始めておりました (^^ゞ
このため大事なポイントの見落としと勘違い判断誤りなどが延々と続くこととなりました。因みに公方屋敷支城方面から、この公方屋敷方面を俯瞰遠望した画像を撮影したつもりでしたが、実際にはコロッと失念していたようで肝心の画像が見当たりませんでした (^^ゞ
城館遺構を遠望も加味してささっと通り過ぎるスタイルの探訪であれば、これらの和田城館群もせいぜい5時間もあれば廻り終えるのかも知れません。しかし仮に徒歩での移動時間も含め1か所1時間としても、7か所で合計にして7時間はかかるという計算ですので元々のプランそのものにかなりの無理がありました。加えて油日駅前の自販機での飲料水購入をうっかり失念しての朝昼抜きというのはやはり厳しいようです。非常食は常に2食分は携行しているのですが、今回は電車移動のため水分補給は現地調達となるという、極めて当たり前の事情に適応できないような年齢となってしまったようです。
( 2018/2/15 )記述
|
公方屋敷 −画像A−
( 2017年12月10日 撮影 )
一般的に公方屋敷と呼称されている西側を除き三方が低丘陵に囲繞された場所で、画像中央からやや左に低木の植込みと現地解説板が所在しています。このように現在も耕作地として利用されていますので、くれぐ゜れも農作物に留意し畦道や水路などを傷めないよう多少遠回りしたりしながら見学することが求められます。
殿山方面へと続く尾根筋 −画像B−
( 2017年12月10日 撮影 )
殿山方面へと続いている東側の丘陵尾根筋で、両側には切落したような形跡が感じられ、このまま登ってゆくと殿山山頂部の木製展望台付近へと到達します。
公方屋敷の解説板 −画像B−
( 2017年12月10日 撮影 )
合併以前の甲賀町当時に作成設置された現地解説板で、鉄骨の錆具合などから推定しますと恐らくは1980年頃のものになるのでしょうか。
国土地理院航空写真より編集加工 −画像D−
( 2017年12月10日 撮影 )
国土地理院の電子国土サイトからダウンロードし手を加えたもので、従来の殿山と殿山城、南の公方屋敷との位置関係などについて簡単に纏めてみました。村田修三氏、中井均氏にりますと、近年新たに確認された殿山城をふくむ和田城館群という捉え方を提起されています。(※「甲賀市史第7巻」「甲賀市史第2巻」)この「城館群」という捉え方が、あくまでも地理的な分布のみを指すものではなく、その機能連携にまで及ぶものとするならば、その背後に存在するであろう同名中、郡中惣などの相応の経済力、軍事力を伴う地域権力の実態解明がとても気になります。
「甲賀市史第2巻」(308頁から310頁)に掲載されている村田修三氏の説によりますと、赤枠で囲んだ公方屋敷の領域の内、少し西側に張出した方形の林(※現在は竹林)がこれに相当します。
|