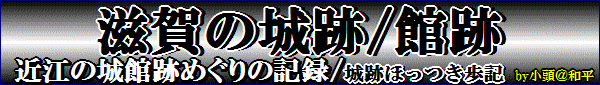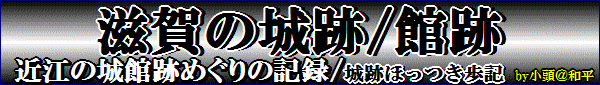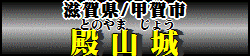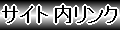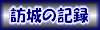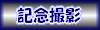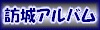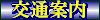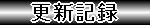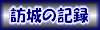 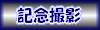
|
凸 近年その存在が確認された遺構
2016年12月に続く滋賀県甲賀市の遠征です。昨年最寄駅から始発の東上線に乗り池袋へ。 山手線経由で東京駅へ向かい、午前6時29分発のぞみ号に乗車。この時点で東上線の始発からは既に1時間半も経過し、乗換待ちのタイムロスは池袋での約15分が一番大きいものがあります。つまりダイヤ上では寧ろ地下鉄丸ノ内線を使用する方が早いのは承知していますが、東京駅構内でのキャリーケース移動距離がやたらに長くなることから、今年は山手線を利用してみたものです。新幹線では昨年同様に一度京都まで向かい、4分間の乗り継ぎで琵琶湖線で草津市内へ戻り駅前のホテルに荷物を預託し、午前9時40分台の草津線にて油日へと向かいました。 1年ぶりに訪れた油日駅では日曜日ということもあり、甲賀忍者に扮した駅業務を委任されている年配の方の歓迎を受けましたが、油日で降りた乗客は自分を含めて数人で、しかも「観光客」らしい姿は自分ひとりと相変わらず閑散とした様子でした。JR草津線も近江鉄道などと接続している貴生川から先では正規駅員は不在で、地元高齢者の方による運営がなされているようで、早朝と夜間は無人となりむろんICカードは使えません。草津市始発の同線は一つ先の「手原駅」で概ねその4割位が下車、その先の貴生川までで更に5割位が下車してしまう様子が窺えます。残念ながらこうして拝見している限りでは終点の柘植まで行く乗客は全体の1割にも満たないようにも感じます。前年が2往復で今回が3往復ですので、大した利用実績にはつながりませんが、たまに沿線を訪れる者にとっても大切な路線です。レンタカーなどの車を利用した方が機動性は発揮できますが、駐車場所探しなどにも苦労しますので、今後もできるだけこの草津線にお世話になる予定です。
近年において「甲賀市史」編纂などに伴う実地調査により、殿山の北西尾根筋先端部にこの小規模ながらもより明確な城館遺構が確認されました。「忠魂碑」が設置されている従来の殿山とは別の性格の城館跡のようですが、その距離の近さからか、いまのところは取敢えず名称の上ではやや紛らわしい名称が付されています。屋根筋の堀切からそのまま土塁へは直接登ることは難しいと判断し、堀切の南側を少しだけ迂回するようにして対岸へと這い上がり、そのまま土塁上を西へとすすんでから、比高差の少なくなった頃合いを見計らい郭内へと降りてみました。ただしこの郭から下方に降りる踏み跡は、そのまま民家宅地内の裏手へと出てしまいます。このことから、再びもと来た堀切まで戻りさらに尾根筋の斜面を這い上がることが必要です。
長享期の佐々木六角氏、その後の同名中の形成過程における和田氏拠点防御、織田氏に追われた佐々木六角氏の潜伏、甲賀郡中惣末期の対織田氏対策など、その築城の背景について勝手な想像がひろがりました。
( 2018/2/10 )記述
|
北側麓から見上げた殿山城 −画像A−
( 2017年12月10日 撮影 )
凸城跡の北麓から見上げたもので整形された郭のラインが肉眼でもはっきりと確認できます。いちおう手持ちの資料用バインダーで直射日光を遮蔽してはいますが、生憎と太陽の位置関係上からハレーション気味の画像となっています。
尾根筋を断ち切る堀切 −画像B−
( 2017年12月10日 撮影 )
画像左が従来の殿山方面で、右側が郭跡側となります。従来の殿山と呼ばれていた個所から直線にして僅か100mほどしか離れていない城館遺構でもあり、しかも中世城館の著名な密集地帯のひとつでもあることなどを勘案しますと、なぜ今までに未確認(あるいは未公表)であったのか些か不思議な感じもします。一部の愛好家などにはかなり以前から既に知られていた存在であったのでしょうか?現在でも切岸の斜度は45度前後を有しており、木の枝や笹に掴まりながら何とか堀底に降りてみました。
南西方向からの遠景 −画像B−
( 2017年12月10日 撮影 )
一般に公方屋敷支城と呼ばれている城館跡の南東麓辺りから撮影した遠景です。城跡の凡その位置は画像中央からやや左上の丘陵先端部付近となります。
殿山城全景 −画像B−
( 2017年12月10日 撮影 )
殿山城の西側約150m付近に所在している公方屋敷支城の藪と格闘してきた後に撮影したものです。
国土地理院航空写真より −画像B−
( 2017年12月10日 撮影 )
国土地理院の電子国土サイトからダウンロードし手を加えたもので、従来の殿山、南の公方屋敷、西の公方屋敷支城との位置関係などについて簡単に纏めてみました。中井均氏によれば、南に散開する和田集落の入口に当たることから和田城館群の監視所的な城郭であろうとされています。(※「甲賀市史第7巻」)
|