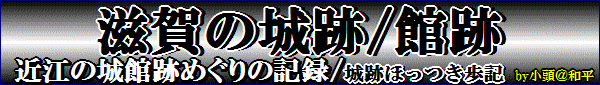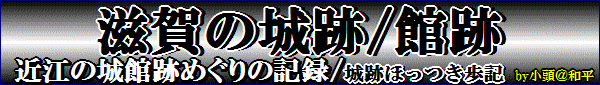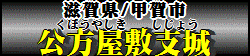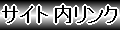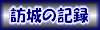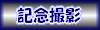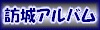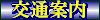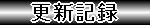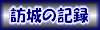 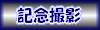
|
凸 タラノキ
現状では主郭付近を除くとほぼ藪城に近いという印象があります。またあまり登り口が明確ではなさそうで、かつ民家近くの斜面を這い上がるようなことから了承をいただくべく声を掛けようにも近くには人影が見当たらず、後ろめたさも加わり気が引けることこの上ありませんでした(^^ゞなお東側から斜面を這い上がりますと、傾斜もそれほどは厳しくはありませんが、途中かなりの藪と有棘植物(タラノキとノイバラなど)が群生する土塁上を通過することになります。このため厚手の手袋なの用意などそれなりの対策注意が必要であるように思われます。ことによると南側の民家方面から、より安全にアプローチするようなルートが存在しているのかも知れないようにも感じました。ちなみに管理人の場合にはノイバラの棘に目を奪われて、除けたタラノキ(小さめの鬼の金棒状をした有棘植物)の反動に右足太腿部を直撃されました。このため1か月間は入浴時に沁みて、2か月後の本項更新時点においても未だ十数か所の赤い直撃痕が残されております (^^ゞ
( 2018/2/12 )記述
|
公方屋敷支城遠景 −画像A−
( 2017年12月10日 撮影 )
和田集落からの帰路に撮影したこの日の最後の方の画像で南東方向の公方屋敷入口付近県道51号線沿いからの遠景です。管理人の場合は画像右下のお宅脇の斜面から失礼をいたしましたが、もしかすると画像左上のお宅の付近からの方が藪漕ぎをすることなくアプローチできるのかも知れません。この位置から眺めますと櫓台のようにも見える整形された二つの土塁地形が際立つアングルで、ちょうど主郭部と推定される削平地の東と西に存在しています。
主郭部とされている削平地付近から南方を望む −画像B−
( 2017年12月10日 撮影 )
この公方屋敷支城を含めて城跡の削平地部分にこうした溜池が設置されている事例は珍しくは無いようで、和田城郭群でも和田城、和田支城1などでも見かけます。この和田城館群以外ではほかに滝川城、新宮城などなどでも見かけていますので特に珍しい存在ではないようです。むろん現在残されている形態は後世の旱魃対策に伴うもののように思われますが、12月という渇水期にこのように満々と水を湛えている光景を目にいたしますとついつい水の手の存在との関係を考えてしまいます (^^ゞ
西側の櫓台地形 −画像C−
( 2017年12月10日 撮影 )
高さは3mほどの長方形をした地形で、本来はもう少し画像右側に延びて西側尾根続きを遮断防御する役割を担っていたものなのでしょうか。「画像A」のうち左手の高台地形に相当します。周辺部はやや足元が柔らかく感じられましたが、画像左側の日の当たっている辺りから登るような仕組みであったのかも知れません。
西側櫓台地形の西側付近 −画像D−
( 2017年12月10日 撮影 )
現在では山仕事などの里道のようになっておりましたが、堀跡のような窪地を伴っているようにも見受けられなくもない城域の西端部分です。虎口部分も明確ではなく和田集落に面した東側などに比べると、西側の尾根続きに対する積極的な防御意図が余り感じられないようにも思われました。画像左側の櫓台状地形の傾斜角はこのように50度前後はありましたが、その反面で斜面自体は比較的柔らかいので実に不思議な感触でした。
主郭部とされている削平地 −画像E−
( 2017年12月10日 撮影 )
東側の土塁状地形は西側の櫓台地形に比べるとやや低く、その平面形状も概ね三角形に近い形状をしていました。主郭部とされている削平地もどちらかといえば城跡らしい印象は余り感じられず、後世の耕作や植林などによりある程度の地形改変が為されているように思われました。
国土地理院航空写真より編集加工 −画像B−
( 2017年12月10日 撮影 )
国土地理院の電子国土サイトからダウンロードし手を加えたもので、従来の殿山と殿山城、南の公方屋敷との位置関係などについて簡単に纏めてみました。中井均氏によれば、近年新たに確認された殿山城とともに和田集落の入口を監視する役割の城郭であろうと推定されています。(※「甲賀市史第7巻」)この「城館群」という捉え方が、あくまでも地理的な分布のみを指すものではなく、その機能連携にまで及ぶものとするならば、その背後に存在するはずの経済力、軍事力を伴う相応の地域権力の解明がとても気になります。
|