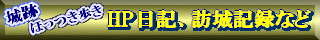
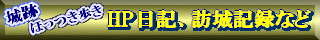
| TOPpageへ | 城跡ほっつき歩きとは | 訪城覚書 | ホームページづくりの日記 | 参考にした資料 | リンク集(お世話になります) |
| 日記の目次 | 工事中 | PAGEの先頭 | PAGEの最後 | ご感想はこちらへ | 工事中 |
(はじめに) | ||

■ 岡部氏の館跡に所在する戦国期と思われる土塁の一部で、その上に見える建物は稲荷神社の社。 ( 2005年5月30日 撮影 ) |
昨日の10時過ぎに生後6週間の5匹の子ネコのうち一匹が二階のベランダ伝いに1階の屋根に下りて地面に転落するという事件が発生。弱々しい鳴声を聞きつけた次男が第一次捜索隊を編成して捜索するもその姿を発見できず。しかる後、再び第2次捜索隊が派遣され、泣き声の方向からその所在を確認するも救出に至らず。 | ||
|
落ちたのはこの子かと思ったのですが、よく似た別の子の方でした。 よく見ると首をやや右に傾けてポーズをとっているようにも思えるのですが。 2005年5月31日 撮影 |
先日開始した展示会の著者の方の本と絵葉書が、なんと昨日1冊と2点売れました。来月の6月にはタウン誌、地域情報誌の掲載三本と三百人程度の団体が来館する予定があるので在庫の補充問題がにわかに懸念され始めました。当初においては著者の方には大変申し訳ないのですが、書店などのリスクを考慮して出版物については同一出版社のものを五種類、各五点ずつという形での委託販売ということに決定したのですが。 | ||

ナデシコ科の越年・多年草のウシハコベ。 ハコベよりも花が大きく草丈も長く、雌しべの白い花柱は5本ある(ハコベは3本)。 2005年5月16日 撮影 |
昔学校で勉強した日本の歴史では十四世紀から十六世紀の関東の戦乱などは殆ど取り扱っていませんでした。なんといっても応仁の乱からいきなり豊織政権にワープするのですから。それも畿内の範囲だけで。 | ||

大勢力の狭間で翻弄された本庄氏の居城本庄城北辺の天然の要害となっていた元小山川の流れ 2005年5月25日 撮影 |
先日開始した展示会の著者の方の本が、なんと昨日1冊、本日1冊売れました。先週の21日の土曜日からスタートしたのですが、火曜日までの3日間は全く売れる気配もなく、結局最終的には1点ずつ自腹で購入することになるのだろうかと思っていたもので...。当方は元々利益ゼロの取り扱いですけれども、書店や出版社の経費のことを考えるとあまり迷惑はかけられず、このまま、順調に推移して最終的に10冊ぐらいは売れてくれると助かるのですが。1点ずつの自腹でも全部で2万円位にはなってしまうので、まずはタウン誌に展示会の情報が掲載される6月が勝負かと(^^; | ||

東方城の郭跡と思われる辺りに生っていたヘビイチゴ 2005年5月25日 撮影 |
(まえがき) | ||

ぼちぼち刈取りの時期を迎える小麦かと。 2005年5月25日 撮影 |
図鑑を調べていたら、名前の由来は庭に咲くセキショウに似ていることから付けられたとあり、セキショウを調べるとこれが掲載されていない...ほかの図鑑を調べて分かりましたけど、不親切というか間が抜けているというか。 | ||
|
竜谷山城への途中の道端に咲いていたニワゼキショウ。花が小さく風もありなかなか焦点が合わず... 2005年5月16日 撮影 |
殆ど手入れをしていない自宅の庭というか僅かな隙間にドクダミが2坪ほど蔓延り、初夏にふさわしいの「白い花」を咲かせました。葉色が赤みを少し帯びた濃い緑色なのでよく目立っています。 | ||
|
ドクダミの「白い花」に見えるのは、中央にある黄色い頭状花を囲む総苞片です。 2005年5月23日 撮影 |
ネコの飼い主の娘が出かけてしまい、少し早起きをして猫たちの様子を見に行くと一匹の子ネコの左目が目ヤニですっかり塞がっていました。仕事の時間が迫っていましたのでトイレの後始末と食料の確認だけして、帰宅してから面倒を見ることに。仕事をしながらも、目ヤニをとるにはまず柔らかいガーゼをぬるま湯につけて、少しずつそっと剥がして上げよう...あっそうだ、確かテーブルの上に殺菌ガーゼがあったような気がするなどと対処方法を考えていました。 | ||
|
生まれたときは耳も垂れていてハムスターにも見えたのがちゃんとネコらしくなりました。生後5週目。 2005年5月22日 撮影 |
仕事先の方で今日から原画展をオープンしました。画集・著書、ジグソーパズルなども同時に販売しますので、多少なりとも売れてくれるといいのですが。初日は広報宣伝の掲載スケジュールの関係などもあり、来館者は午前中にパラパラときたもののその後は静寂の時に包まれました。この場所は鉄道の駅から遠く公共交通機関もないに等しく交通アクセスの利便性に大きな問題があり、あわせてかなり分かりにくい場所に所在しています。このように集客力に乏しい条件下での開催のため、公的施設で入館料無料とはいえ長期的な視野にたったバランスの取れた経営の実現が非常に難しい状況です。 | ||

埼玉県入間郡毛呂山町 毛呂氏館のある長栄寺 遺構は裏山の中腹の林の中に 2005年5月16日 撮影 |
アクセス解析開始してから3ヶ月が経過しました。その中で初めての訪問者の方が非常に多いことが分かります。また、この間に100回以上もご覧いただいている方が何と157人もいらっしゃるようです。更にブックマークからのアクセスが一日平均15件以上も。こんな貧弱なマイナーなサイトにおいでいただき誠に恐縮する一方で、ものすごく感謝しております(^^; | ||

埼玉県入間郡毛呂山町 毛呂城(山根城)の石碑近くの風に揺れるヤグルマギク 2005年5月16日 撮影 |
昨日は仕事中に次第に右ひざの痛みが増幅し通勤の帰りがけに整骨院に立寄って必要な処置をしてもらい、ついでに松葉杖も借りてくるという事態になりましたので、本日は溜まっている振替休みを取って一日中養生ということに。できるだけ歩かないのが早く治癒するとのこと。一日中殆ど動かなかったおかげで大分痛みも弱まってきた感じですが、仕事に行くとそうも行かないので、結果的に休んでおいて正解だったようです。 | ||

埼玉県入間郡毛呂山町の斉藤実盛の子孫とされる斉藤氏の館跡の北側の土塁と空堀 2005年5月16日 撮影 |
(まえがき) | ||

毛呂山町資料館西側の旧鎌倉街道上道と推定される古道と道端に咲いていたミツバツチグリ 2005年5月16日 撮影 |
昨日は仕事で会議があり飯能市まで出かけましたが、会議室の席上から名栗川沿いの新緑の稜線が目に入り、おっ、そうだ、そうだ中山家範の屋敷跡はこの近くだったなどと思い出したものの、時間も、資料もデジカメもないので訪城はまたの機会ということに。 |
前娘の部屋、現ねこ部屋となっている、元自分の部屋にネコどもの様子を窺いにいくと、部屋の前に人が近づいた時点で母ネコのポミが不審者かどうかの検問のために待機しているようです。さて、子ネコたちはというと母ネコが動くものだから一緒になって移動するらしく、白と黒の固まりになってすぐに足元にまとわりついてきます。好奇心が旺盛なようで、くれぐれも踏まないようによく注意して部屋に入らなくてはなりません。 | ||


全員で部屋中を動き回っていますが、小走りに走る子も。生後ちょうど3週間。 2005年5月12日 撮影 |
膝の痛みに加えて、以前からの足のむくみも余りよくなく連休も明けたので早速医者通いに。結局、足の血流と血管の状態を調べるためにMRIを受信することに。軽い脳血管障害の方で以前に3回ほど受信しているので、別にどうということもないのですけれども、連休の直前には足首の踝が見えなくなるぐらいにむくんだりして、いやもう痛切に年齢を感じています。むくんだ足を時々眺めつつ、久しぶりに訪城記録の整理を行い雉岡城をUPしました。 | ||

自宅玄関脇のアメリカフウロ(ゲンノショウコの仲間)で、夕方には小さな花を閉じていました。 2005年5月9日 撮影 |
下の写真の北条氏邦の乗馬姿の像はおぼろげな記憶を辿るとたぶん三十年前ぐらいからあったような気がします。ただ、写真から見ても分かるようにかなり綺麗ですので、二代目あるいは化粧直しをしていると思われます。また、説明の看板も新しいようです。世間一般では、北条氏といっても鎌倉時代の方が有名かもしれません。天正十八年の秀吉の関東侵入の時の攻防についても鉢形城の戦いはどちらかといえばローカルな部類にふくまれているようで、決してそれほどよく知られているというわけでもありません。 | ||

寄居町の国道254号線沿いにある北条氏邦の乗馬像。 2005年5月7日 撮影 |
(往路の独り言) | ||
|
雉岡城(八幡山城)。城跡の中に何故か鳥小屋があり、チャボとシラコバトとそして雉もいました。 2005年5月7日 撮影 |
20年ぶりぐらいの完全な5連休。膝の調子もいまひとつで、左のアキレス腱にも違和感が出てきて、加えて頭が仕事モードに切り替わらず、ひたすらボーッとしているうちに一日が終わってしまいました。一応それなりに仕事はしたつもりですが...休みは精々連続2日までがいいようです。元に戻すのに相当の時間がかかるようで...(^^; | ||

クヌギ、コナラの平地林。 2005年5月5日 撮影 |
2週間が経過して子ネコたちがちょこまかと動くようになりました。昨日の時点ではそれほど動きが早くなかったのですが、今日は全員で動き回るようになり、気をつけないと踏みそうになるので、座るときは数を数えてから出ないと危ない状態です。 | ||

何とか花の盛りに間に合った藤の花。 2005年5月5日 撮影 |
ポミの産んだ子ネコたちがようやくよちよちと歩くようになりました。まだ、自由に歩けるというわけではなく、後ろ足を震わせ少し怖がりながら母ネコの周囲50センチぐらいの範囲で動いています。 | ||
|
授乳中のポミと5匹の子ネコたち。動きが早いもので残りの2匹は何れまた... 2005年5月4日 撮影 | ||
|
|