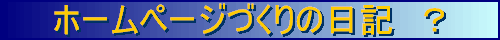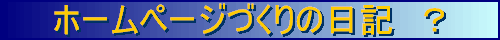| ・2005年3月28 小雨に煙る花園城と花園御嶽城 |
|
(まえがき)
前日から入念に資料に目を通し、道路地図も飽きるぐらいに何度も確認し最低3か所程度は訪城しようと企んでいたのですが、残念ながら天気予報を見る限り降水確率は70%前後となっていました。休みの日にもかかわらず珍しく7時前に目を覚まし、新聞を取りに外へと出ると、予報どおり小雨がパラパラ。ひどく濡れるというほどではありませんでしたが、市町村別の予報を幾つか確認してもやはり降水確率は70%前後。しかし、念のため東京電力の雨量観測のページを確認すると、花園城のある寄居周辺は少なくとも午前中ぐらいは纏まった雨はなさそうな期待が持てることが分かり、とっとと訪城の支度を。前日に手配して置けばよかったのですが、かなりの急斜面がありそうなので出掛けに近所のホームセンターで安全作業用の手袋を1980円で購入。これがあとで非常に役立ったのでありました。
さて、お彼岸の渋滞もなく目的地の花園城の麓に着いたのは、途中コンビニで買い物をしたにもかかわらず予想通りの午前10時30分。ここまで全て順調。経路の関係で途中鉢形城を縦断する県道を通過すると「北条祭」の関係でしょうか、スポンサー名の入った雪洞が県道沿いにプラスチック製のさくらの枝と共に立てられていました。鉢形城はと見ると東の端にある笹曲輪の辺りも大分整備されたようで、城址公園化も着々と進行しているようです。また、県道から馬出の辺りをふと見上げたら黄色いノボリバタが翩翻と翻っていました。
荒川にかかる鉄橋の「おりはら橋」を渡って国道140号線を横断すると目の前に花園城のあるはずの山が、存在感を漂わせて小雨に煙っていました。秩父鉄道の踏切を渡り線路沿いに行き止まりの道路の突き当たりの左端に車を止め登り口を物色。この辺りからもいけそうな感じですが、確実に諏訪神社の裏側辺りから頂上を目指すことに。
■花園城
諏訪神社の境内は、南側に少林寺川の小河川を配して更に二段構えの平場が形成されており、もう少し広ければ居館などの根古谷などの存在を想定できそうな地形となっています。神社の向かって右手にある稲荷神社の祠の脇から山腹を左斜めに登っていく道が見えますので、ここから花園城へ向かいました。10分も進まない内に樹木枝と藪のために視界がさえぎられ、南側斜面に相当数存在すると思われる大小の腰郭はその殆どを確認することができません。更に西側に向かい登って行くとたぶん最大規模の竪堀と思われる遺構に直角にぶつかりました。道はそのまま竪堀を横断しているようですが、その竪堀の少し手前を右に登っていく踏み跡がありましたので、こちら側から二の郭南側の石積目立つ腰郭の上部に到達。
そのあと稜線を目指して二の郭に這い上がり、とりあえず現在位置を確認するために土橋状の狭い道を通り本郭へ進みましたが、やはり花園城のメインは何といってもこの堀切でしょう。荒削りの岩肌が露出する堀切にひたすら感動しながら、本郭の西側の石碑の所で記念撮影を。西側にある本郭の位置をつかめたので、県の埋文センターで作成した最新の縄張り図のコピーを参照しながら、以下二の郭、三の郭、東郭と堀切を横断し東側の城跡の縄張り先端部の堀切を確認してひと段落。
しかしそのあと性懲りもなくまた本郭まで戻りよりによってもっとも急斜面の西側斜面を駆け下りました。この時に足備えのトレッキングシューズと出掛けに近くのホームセンターで購入した作業用の安全手袋が大いに役立つことになりました。小雨の降りしきる状態ですので、滑らないように木の枝に掴まりながら駆け下りるのですが、腰郭群を過ぎた辺りから道というより只の急斜面となり、止まるにとまれずスピードは上がる一方で県道予定地の平坦地まで転がるように勝手に足が進んでいきました。ちなみに参考に持参した縄張り図のコピーはこの県道建設に伴う発掘調査の時のもののようです。
縄張り図から周辺の地形を含めて比高差80m程度と分かりきっているからできる芸当で、地形不明の上に比高差が300m以上あったらかなり危険です。さてここで眼前に少林寺川の小さな流れがありましたが、渇水期で水深も殆どなく苔むした石で滑らないように注意しながら、前に通った方と同様に背丈ほどの高さの土手を這い上がって公道へと戻り昼食に向かいました。といっても車の中で途中ローソンで購入したサンドイッチと自宅から持参した特売59円の「おーいお茶」で済ましただけですけど。
■花園御嶽城
花園城の北西の少林寺の裏山ですが、尾根筋で繋がってはいませんので一度麓まで下山しますが、車で少林寺の駐車場まで行けるというお気楽なコースです。花園御嶽城の方が花園城よりも40メートルほど高いのですが、車で途中までいけますし、五百羅漢の石像に挨拶してるうちに円良田湖へ抜ける峠に到着しますので20分程度の登りですがあっという間の時間です。
この峠の所から一旦西側に進み円良田湖への道はそのまま北へ向かいますが、花園御嶽城へは真直ぐ西側の山頂を目指します。一見遠くに見えるようですが、この場所からの比高差は40メートルぐらいですので10分足らずで東側の二の郭に到着します。途中の道は思ったよりも踏み跡もしっかりとしており、夏場でもなければ道に迷うこともないでしょう。また途中に山頂の本郭に向かって左側の山腹に人工的な細い帯郭状の多数の段築が見えますが、この場所からの写真撮影は単なる藪の写真になりますのでここは自重して、二の郭のところに別の所から上ってくる神社の参道を少し下った辺りで、左側の山腹を観察すると石積みのある段築がはっきりと見えます。
本郭へは神社の石段を登っていきますが、途中の眷属の狐の表情が大変印象的です。本郭のある山頂は御嶽山信仰石碑が所狭しと並んでいます。石碑自体の年代は明治期から昭和30年代のもので比較的新しいのですが、全体として苔むしたように見えることもあり、入口の所の二体の眷属の狐の表情と相俟ってなかなか凄みのある気配が辺りを漂っていました。なお、本郭の北側と西側には腰郭や竪堀、構堀などが思いのほかよく遺されていることに間道を覚えつつ、そのままもと来た道を引き返しました。
(おしまい)
一般に山城だけでなく山道の登りに要する時間は比高差100mにつき20分前後だと思います。また下りの場合には勾配の程度にもよりますがだいたいその六割前後と考えれば良さそうです。ただ登りの場合で比高差が300m以上の場合には、体力の消耗を考えると少なくとも10分程度の小休止が必要です。この時は大して影響を感じませんでしたが、この花園城の12分間の下りがかなり後になってからじわじわと影響。花園御嶽城からの帰路の五百羅漢の下り坂の階段状の山道で明らかに膝に違和感と疲労を感じ、雨も予想通り少し強くなってきましたので、時間に未だ余裕はあるものの三ヶ所目の訪城を断念することに。やはり体重の相当な減量が必要なようです。
|