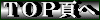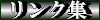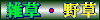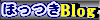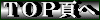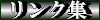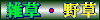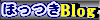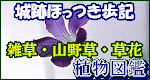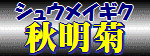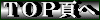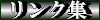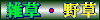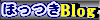| 日本名 |
秋明菊(シュウメイギク)
⇒秋に開花する菊に似た花を咲かせることから名づけられたとされるが、画像のように白花で一重咲きのものに関してはあまり似ているという印象は感じられない。 |
| 科/属 |
キンポウゲ科イチリンソウ属
⇒この白花で一重咲きタイプのものからは、同属であるイチリンソウに似ているといったような印象は余り感じられない。 |
| 学名 |
Anemone hupehensis var. japonica(=Anemone japonica) |
| 開花時期 |
図鑑などでは一般に8月から10月としている場合が多く見かけられるが、実際には11月上旬頃まで咲いているような場合も少なくない。 |
| 特徴など |
低山の林縁に生育する耐寒性の多年草で、古い時代にヒマラヤ、中国、台湾、マレー半島から渡来したともされていて、かつては西日本において人里近くに野生化しているものが多いとされていたが、近年では日本全国に帰化していることが確認されているようである。(⇒「色で見わけ五感を楽しむ野草図鑑/ナツメ社」などより)
草丈はおおむね50センチメートルから80センチメートルほどの高さとなり、花径は3センチメートルから8センチメートルほどやや幅がある。
花弁のように見えるのは萼片であり、地下茎が長く伸びて株全体に産毛がめだつ。
八重咲で赤花タイプのものは確かにキクに似ていなくもないが、花色には白花のほかに薄赤紫、紫色、紅色などの品種が多くみられる。
なお園芸種のチャボシュウメイギクは矮性化していて30センチメートルほどと草丈が短い。
有毒とされているので要注意。(⇒「散歩の花図鑑/新星出版社」より)
花言葉は「薄れゆく愛」「耐え忍ぶ愛」 |
別名
俗名
方言 |
代表的な別名としては「貴船菊」「黄船菊」(以上キブネギク)が知られ、漢字表記にも「秋冥菊」「秋名菊」(以上シュウメイギク)があり、このほか秋牡丹(アキボタン)、草牡丹(クサボタン、秋芍薬(アキシャクヤク、シュウシャクヤク)、高麗菊(コウライギク)、唐菊(トウギク)などといった呼称があるという。また、その英語表記からジャパニーズ・アネモネと呼ばれることもある。
なお代表的な別名である「貴船菊」は、かつて京都市北部の貴船山周辺に多く見られたことから名づけられた(⇒「野草大百科/北隆館」などより引用した) |